「日経Linux(リナックス)2016年5月号」を編集部よりいただきました、ありがとうございます。執筆を担当させていただいた「すぐ試せるサンプルがいっぱい 楽しいラズパイプログラミング」の連載第1回目「LEDとスイッチを使ってみよう」が掲載されています。目次は「日経Linux – 本誌目次 – 2016年5月号:ITpro」にあります。
(ラズパイをこれから始める人は「ラズパイ ( Raspberry Pi ) を始めるときに用意したいもの | hiro345」もどうぞ。)
続きを読む
「日経Linux(リナックス)2016年5月号」を編集部よりいただきました、ありがとうございます。執筆を担当させていただいた「すぐ試せるサンプルがいっぱい 楽しいラズパイプログラミング」の連載第1回目「LEDとスイッチを使ってみよう」が掲載されています。目次は「日経Linux – 本誌目次 – 2016年5月号:ITpro」にあります。
(ラズパイをこれから始める人は「ラズパイ ( Raspberry Pi ) を始めるときに用意したいもの | hiro345」もどうぞ。)
続きを読む
最新のRaspbianではWiringPiが同梱されているので、WiringPiをスタティックリンクしたいという要望はあまりないかもしれませんが、自分が作成したアプリにおいてWiringPiのバージョンを固定にしておきたい、といった要望があるときには、知っておくと便利です。方法は、WiringPi/INSTALL at master · WiringPi/WiringPi · GitHubにある通り、スタティックライブラリをビルドする専用のコマンドがあるので、これで作ればよいそうです。
続きを読む
CentOS7へのdocker導入について調べました。「Docker Docs」にあるドキュメントから調べていくのが良さそうです。プロダクトが複数になってきていて、わかりにくいのですが、従来のdockerコマンドはDocker Engineに含まれているようなので、これをインストールすることにしました。ちなみに、OS XやWindowsユーザーなら、Docker Toolboxを導入するのが一番手っ取り早いようです。Linuxの場合は、Docker Toolboxに含まれるKitematicのLinux版がないようなので、必要な物を個別に導入するということになります。
CentOS7からWindowsマシンのリモートデスクトップを利用しようと思って、調べてみました。リモートデスクトップは、RDP ( Remote Desktop Protocol ) で接続します。事前に Windows 側でリモートデスクトップ接続の許可をしておく必要があります。また、Windowsの方はProfessional版などのリモートデスクトップを提供する機能を持つバージョンが必要です。リモートデスクトップクライアントは、どのWindowsエディションでも使うことができます。
続きを読む
コンピュータのメンテナンスは計画的にしたいものですよね。OSのアップデートが何時頃にあるのかは大体わかりますから、それに合わせてハードウェアを用意したり、移行にあたって必要な作業の整理をしたり。もちろん、自分も計画は立てたんですよね。CentOS7がリリースされてから先行導入を開発用マシンにして、大体良さそうになったところで運用マシンへHDDを増設してアップデートしようって。ただ、当時、結構時間の確保ができなくて、先延ばしになってました。気がついたら2016年4月。少し遅くなりましたが、2016年4月2日に思い立って実施しました。
続きを読む
「日経Linux(リナックス)2016年4月号 」を編集部よりいただきました、ありがとうございます。執筆を担当させていただいた「楽しく学ぶラズパイプログラミング」の連載第6回目(最終回)が掲載されています。目次は「日経Linux – 本誌目次 – 2016年4月号:ITpro」にあります。
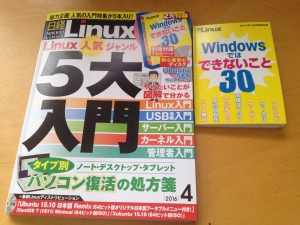
(ラズパイをこれから始める人は「ラズパイ ( Raspberry Pi ) を始めるときに用意したいもの | hiro345」もどうぞ。)
続きを読む
「日経Linux(リナックス)2016年3月号 」を編集部よりいただきました、ありがとうございます。執筆を担当させていただいた「楽しく学ぶラズパイプログラミング」の連載第5回目が掲載されています。
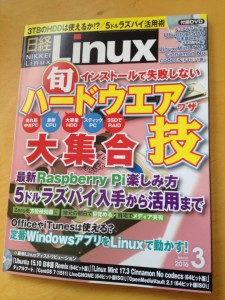
続きを読む